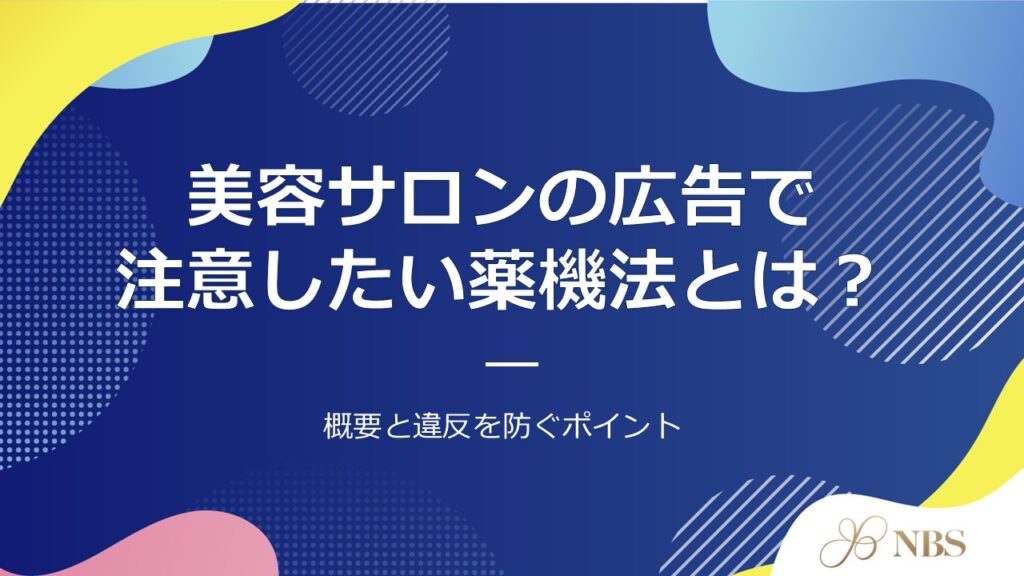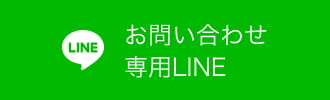美容サロンでは、マシンや物販商品の宣伝を行いますが、このとき注意しなければならないのが「薬機法に触れる広告表現」です。万が一、広告で使用した表現が薬機法違反と見なされれば、法的な責任が生じかねません。
そこで今回は、薬機法について解説するとともに、美容サロンが気をつけたい広告規制について詳しく解説していきます。広告表現で違反しないためのポイントもまとめているので、あわせてご覧ください。
薬機法とは

薬機法は、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、かつての薬事法を改正し、施行された法律です。この法律は、以下の製造、販売、流通、広告に関するルールを定めたもので、国民の健康と安全を守ることを目的としています。
- 医薬品
- 医療機器
- 化粧品
- 医薬部外品
- 再生医療等製品
消費者が不利益を被らないためのルールなので、誠実な事業運営のため、事業者が必ず理解しておくべき法律の一つです。
美容サロンが気をつけたい薬機法の広告規制

美容サロンの広告では、とくに、以下2つの規制に注意しなければなりません。
- 虚偽・誇大広告等の禁止
- 承認前医薬品等の広告の禁止
薬機法における広告の定義とあわせて、確認しておきましょう。
【薬機法】広告の定義と規制の対象
薬機法における広告は、以下の条件で定義されます。
- 顧客の購買を誘導する意図がある
- 対象製品の名称が明示されている
- 消費者が認識できる状態で表示されている
これには、チラシや看板のほか、アフィリエイト記事、Webサイト、SNS広告、DMなどが含まれます。これらに関わったすべての人が広告規制の対象になり、広告の依頼主や作成者、実際に紹介する人など全員に責任が生じます。
虚偽・誇大広告の禁止
薬機法では、虚偽または誇大な表現によって、消費者の誤解を招くような広告は厳しく禁止されています。たとえば、「必ず痩せる」「1回でシミが完全に消える」といった表現は、科学的な根拠がない限り、虚偽・誇大とみなされます。
また、実際より高い効果を感じさせる言い回しや、不適切なビフォーアフター写真の使用も、誇大広告と判断されるでしょう。美容サロンでは、物販商品や機器をアピールする際に、「効果には個人差があります」のような文言を添えるなどして、消費者への誤認を防ぐ配慮が必要です。
承認前医薬品等の広告の禁止
薬機法では、国の承認・認可を受けていない医薬品等の名称や効能などについて、広告することを禁止しています。また、医薬品ではないものを、それと誤認させるような表示も、違法になる可能性が高いです。
たとえば、「薬用」や「医師が認める」などの表現を用いた場合、その根拠となる承認などがなければ薬機法に抵触するでしょう。美容サロンでは、輸入品やオリジナル製品を扱う機会も多いため、取り扱う製品の詳細を事前に確認することが大切です。
薬機法に違反したらどうなる?

薬機法に違反すると、行政指導や刑事罰の対象となる可能性があります。違反に対して段階的に行政指導が行われ、改善命令や業務停止命令が出されます。
これらの命令に従わなければ課徴金納付命令が下り、虚偽・誇大広告の禁止に違反した場合には、該当する期間の売り上げの4.5%を支払わなければなりません。また、刑事罰では、違反行為に応じて、罰金や懲役刑が課されます。
違反が公に知られれば、顧客や取引先の信頼を大きく損ない、経営そのものに深刻なダメージを与えかねません。経営者の責任が問われるため、事前に薬機法の内容を正しく理解し、全スタッフに周知徹底しておくことが重要です。
美容サロンは医師法と景品表示法にも注意
美容サロンの広告では、薬機法のほか、医師法と景品表示法にも注意しなければなりません。
医師法における広告規制
医師法には、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と記されています。美容サロンの広告において、医療行為と誤解されるような表現は、医師法違反とみなされる恐れがあります。
たとえば、「ニキビ予防」「アトピーを改善」のような表現は、たとえ実際に効果があっても、美容サロンで使用するのは不適切です。また、脱毛サロンで「永久脱毛」という表現を使うことも、医療行為を連想させるためNGとされています。
このように、医療との線引きが不明瞭だと、法的リスクを招きかねないため注意が必要です。
景品表示法における広告規制
景品表示法は、消費者に対して不当な表示や過大な景品を提供することを禁止する法律です。美容サロンにおいては、とくに「優良誤認表示」と「有利誤認表示」に注意しなければなりません。
たとえば、「98%が効果を実感」などの表現は、客観的なデータがなければ不当表示に該当する可能性があります。また、実際には割引していないのにも関わらず、「通常価格の10%OFF」などと謳う行為も認められません。
うっかり使いがちな「No.1」や、「日本一」のような最上級表現も、優良誤認違反に該当します。
【美容サロンの広告】違反しないためのポイント

美容サロンを経営する上で、広告の運用は重要です。広告で法律に違反しないよう、運用のポイントを確認しておきましょう。
問題ない表現か確認
広告の作成においては、その表現が法的に問題ないかどうかを、事前に確認することが求められます。たとえば、次のような表現は、薬機法や医師法に抵触する可能性があります。
- 小顔になる
- 脂肪を燃やす
- シミを治す
医療行為ととられる表現を避け、効果を断言しないなど、慎重に言葉を選びましょう。また、エビデンスがある場合は必ず併記するほか、お客様の目に触れる前に第三者の視点を用いてチェックすることも大切です。
必要に応じて薬機法チェックツールなども活用し、誤解を与える表現を避けてください。
すべての媒体に気を配る
違反リスクは、紙の広告だけでなく、以下のようにあらゆる媒体に及びます。
- Webサイト
- SNS
- LINE公式アカウント
- ブログ
- 動画 など
とくにSNSでは、日常的な投稿に広告表現が混じることも多く、意図せず違反してしまうケースがあります。たとえば、スタッフの個人アカウントであっても、規制対象になるので注意が必要です。
それぞれの媒体における表示ルールを整理し、事前に社内で共有・管理する体制を整えて、リスクを回避しましょう。薬機法のチェックリストを作成し、スタッフ全員に研修を実施するといった対策が有効です。
専門家に相談
美容サロンは、広告への行政指導や注意喚起、顧客からの問い合わせに備えて、対応フローを明文化しておく必要があります。また、これらの対応には、状況に応じて外部の専門家と連携がとれることが大切です。
たとえば、広告の作成段階において、表示に法的なリスクがないか不安な場合は、法律や業界規制に詳しい弁護士や行政書士、広告審査のコンサルタントなどに相談するとよいでしょう。初回の広告審査をプロに任せ、どこに問題があるか、どう改善すべきかを知っておけば、以降の広告作成がスムーズに行えます。
最新の法改正や行政の動きに対して、社内のリソースだけで対応するのは困難ですが、外部に依頼すれば、負担を抑えながら適切な対策がとれるのが利点です。トラブルが起きてからでは対応が遅れる可能性があるため、開業前や新サービス導入時など、節目ごとに確認するのが理想です。
専門家への相談は、コストはかかるものの、信頼とリスク回避への投資と考えると有効な手段といえます。
美容サロンの広告は薬機法に注意
美容サロンの広告において、安易に「効果を高く印象付ける表現」や「国の承認を受けていない医薬品等の宣伝」を行うと、薬機法に触れる可能性があります。薬機法に違反した場合は、行政処分や刑事罰の対象になるため、十分に注意しなければなりません。
また、医師法や景品表示法などにも抵触しないよう、さまざまな表現に気を配る必要があります。社内で広告表示に関するルールをしっかり定めるほか、専門家に相談するなどして、適正な表現が行えるように工夫しましょう。
誠実な広告表現は、お客様の信頼を高め、安定したサロン経営につながります。